新築の注文住宅を建てる際、デザインや間取りにワクワクするのはもちろん、「防犯対策」について真剣に考える方も多いのではないでしょうか?
昨今、外国人による治安悪化のニュースも多いですし、家族の安全な暮らしを守るための防犯カメラの設置は、多くの方が一度は検討するテーマだと思うんですよね。
しかし、「本当に自宅に必要なのか」「後付けでも良いのでは?」といった疑問や、費用、機種選び、プライバシーへの配慮など、考えるべき点は多岐にわたります。
この記事では、注文住宅における防犯カメラの必要性から、後悔しないための具体的な設置計画、費用の相場、そして機種の選び方まで、専門的な知識を基に網羅的に解説します。
あなたの理想の家づくりにおける、最適な防犯対策を見つける一助となれば幸いです!
- 防犯カメラの必要性と設置のメリット・デメリット
- 新築時に最適な防犯カメラの設置計画と注意点
- 機種選びから配線・費用までの具体的なポイント
- ワイヤレスやDIY設置の可能性とリスク
注文住宅で防犯カメラを検討する際の基礎知識

注文住宅のソコが知りたい・イメージ
ここでは、防犯カメラの設置を考える上で知っておきたい基本的な情報を解説します。
現在の設置割合や、設置に否定的な意見、そして導入した場合の利点と欠点など、多角的な視点から防犯カメラの必要性を考えていきましょう。
防犯カメラを設置している家の割合
自宅に防犯カメラを設置することへの関心は年々高まっていますが、実際の設置割合はどの程度なのでしょうか。
2018年に実施された綜合警備保障(ALSOK)の調査によれば、自宅に防犯カメラを設置している人の割合は23.8%でした。

ただし、この数値には集合住宅などで最初から備え付けられていたケースも含まれています。
自身で能動的に防犯カメラを設置したという人に絞ると、その割合は7.4%に留まり、まだ一般的とまでは言えない状況がうかがえます。
一方で、防犯カメラの映像が犯罪解決の決め手となるケースは増加傾向にあります。実際に、警視庁が公表したデータでは、主要な繁華街に設置された防犯カメラにより、930件の録画データのうち471件が検挙活動に活用されました。
このようなニュースを目にすることで、個人の防犯意識も高まり、一般家庭での導入を後押ししていると考えられます。
また、自治体によっては防犯カメラの設置費用の一部を補助する制度も存在し、これも普及の一因となっています。
これらの背景から、防犯カメラは私たちの暮らしにおいて、より身近で重要な存在になりつつあると言えます。
新築に防犯カメラはいらないという意見も

注文住宅のソコが知りたい・イメージ
一方で、防犯カメラの重要性が高いといっても、全ての人が設置を望んでいるわけではありません。「新築に防犯カメラはいらない」と考える方々にも、いくつかの明確な理由が存在します。
最も多い理由の一つが、住んでいる地域の治安に対する信頼です。
犯罪発生率が低く、住民同士のコミュニティがしっかりと機能している地域では、カメラによる監視の必要性を感じにくいかもしれません。
また、窓に防犯フィルムを貼ったり、補助錠を取り付けたりといった物理的な防犯対策で十分だと考える方もいます。
コスト面も大きな要因です。注文住宅の建築中は何かと出費がかさむため、数十万円にもなり得る防犯カメラの設置・維持費用は避けたいという意見は少なくありません。
さらに、心理的な側面も無視できません。
常に監視されているような感覚が落ち着かない、家族や来客に窮屈な思いをさせてしまうのではないか、といったプライバシーへの懸念から設置をためらうケースもあります。
これらの意見は、防犯カメラを検討する上で必要性を慎重に判断するための重要な視点となります。
設置するメリット・デメリットを比較解説
防犯カメラの設置について、その利点と欠点を正確に理解しておくことが不可欠です。
防犯カメラには、犯罪抑止や安心感といった大きなメリットがある一方で、設置費用やプライバシー問題といったデメリットも存在します。
防犯カメラのメリット
最大のメリットは、やはり「犯罪の抑止効果」です。
防犯カメラが設置されている家は、侵入窃盗犯から「防犯意識が高い家」「証拠が残るリスクのある家」と認識され、ターゲットから外されやすくなります。
万が一、被害に遭ってしまった場合でも、録画映像が犯人特定や状況証拠として活用できる可能性もあります。
また、スマートフォンと連携できる機種を選べば、外出先からでも自宅の様子を確認でき、留守中の安心感につながります。
子どもの帰宅確認や、不審者への声かけ機能など、家族の見守りツールとしても役立つでしょう。
防犯カメラのデメリット
デメリットとしては初期費用と維持費が挙げられます。本体価格に加えて工事費や、クラウド保存サービスの月額料金などが発生します。
また、カメラの設置角度によっては近隣住宅が映り込み、プライバシー侵害のトラブルに発展する可能性もゼロではありません。
カメラがあることへの過信から、基本的な戸締りなどがおろそかになるリスクも考えられます。
防犯カメラの長所&短所一覧表
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 防犯性 | 侵入窃盗などの犯罪抑止効果が高い 万が一の際の証拠映像として活用できる |
カメラの死角を突かれる可能性がある カメラがあることで逆に狙われる可能性も |
| 利便性・安心感 | 外出先からスマホで映像を確認できる 子どもの帰宅確認など家族の見守りに使える |
監視されているようで落ち着かないと感じる場合がある 定期的な映像確認やメンテナンスの手間がかかる |
| コスト | 自治体によっては設置補助金制度が利用できる | 初期費用(本体・工事費)と維持費(電気代・保守費)がかかる |
| 近隣関係 | 地域の防犯にも貢献できる可能性がある | 近隣住民のプライバシーを侵害し、トラブルになるリスクがある |
これらの点を総合的に比較検討し、ご自身の家庭にとって設置が本当に有益かどうかを判断することが大切です。
犯人特定期間と映像の保存期間・復元

注文住宅のソコが知りたい・イメージ
防犯カメラを設置する大きな目的の一つに、犯罪が発生した際の「証拠確保」があります。しかし、映像が確実に犯人特定につながるかどうかは、いくつかの要因に左右されます。
犯人特定を左右する映像の質
犯人特定において最も鍵となるのは、映像の「画質」です。
不審者の顔や服装、あるいは車両のナンバープレートなどを鮮明に識別するためには、最低でも200万画素(フルHD)以上のカメラを選ぶことが重要です。
画素数が低いと、映像を拡大した際に不鮮明になり、個人を特定するのが困難になります。
また、夜間の撮影能力も重要で、赤外線機能などにより暗闇でもはっきりと対象を捉えられる機種が望ましいです。
犯人が特定されるまでの期間は事件の状況によりますが、鮮明な映像があれば、捜査の初動段階で有力な手がかりとなり、早期解決に繋がる可能性が高まります。
録画データの保存期間と復元の注意点
防犯カメラの映像は、レコーダーに内蔵されたハードディスク(HDD)やSDカードに保存されるのが一般的です。
保存期間は、HDDの容量、カメラの台数、画質設定などによって大きく変動し、一般家庭では数週間から2ヶ月程度が目安となります。
HDDの容量がいっぱいになると、古いデータから自動的に上書きされていくため、何かあった際には速やかに映像を確認し、必要な部分をバックアップすることが不可欠です。
一度上書きされてしまったデータの復元は、専門業者に依頼しても極めて困難か、不可能に近いのが実情です。
いざという時に「録画されていなかった」という事態を避けるためにも、少なくとも週に一度は録画が正常に行われているかを確認する習慣が大切になります。
防犯カメラは新築時設置がおすすめな理由
注文住宅を建てるなら、防犯カメラの設置は建築計画の初期段階で検討するべきでしょう。
後から設置することも不可能ではありませんが、新築時に計画しておくことで、多くのメリットを享受できるからです。
最大の利点は、配線を壁の内部に隠せることです。後付け工事の場合、電源やLANケーブルを壁の表面に這わせる「露出配管」にならざるを得ないことが多く、せっかくこだわった住宅の外観を損ねてしまう可能性があります。
壁内に配線を通すことで、ケーブルが雨風にさらされず、劣化や損傷のリスクを低減できるという耐久面でのメリットもあります。
また、建物の構造や性能への影響を最小限に抑えられる点も大きなポイントです。
後付けで壁に穴を開ける場合、建物の断熱性や気密性を損なうリスクが伴います。不適切な工事は、外壁の防水シートを傷つけ、雨漏りの原因になることさえ考えられます。
新築時にハウスメーカーや工務店と連携して工事を進めれば、建物の性能を維持したまま、安全かつ確実にカメラを設置できます。
さらに、設置場所の自由度が高く、コストを抑えられる可能性もあります。
後付けでは難しかった場所に、最適な画角でカメラを設置できるほか、建築工事の一環として行うことで、単独で業者に依頼するよりも工事費用が割安になるケースもあります。
これらの理由から、防犯カメラの設置は、後悔しない家づくりのために、新築計画に盛り込むべき項目の一つと言えるでしょう。
注文住宅の防犯カメラで失敗しない設置計画

注文住宅のソコが知りたい・イメージ+
防犯カメラの性能を最大限に引き出すためには、設置計画が最重要といっても過言ではありません。
ここでは、配線やコンセントの位置、機種の選び方や費用など、注文住宅で防犯カメラを導入する際の具体的なポイントを解説します。
防犯カメラの新築時における配線と空配管
注文住宅に防犯カメラを設置する際、最も安定した運用が期待できるのは有線タイプのカメラです。
ワイヤレスカメラは手軽さが利点ですが、電波状況によっては映像が途切れるリスクが伴います。その点、有線カメラは録画機まで物理的なケーブルで接続するため安定した映像の送受信が可能です。
この有線カメラのメリットを最大限に活かすためには、新築時の「配線計画」が鍵となります。
玄関や駐車場、庭など、監視したい場所に合わせてカメラの設置位置を決め、そこから録画機を置く場所まで、壁の中や天井裏を通る配線ルートをあらかじめ設計しておくのです。
こうすると、ケーブルが外に露出することなく、住宅の美観を保つことができます。
将来を見据えた「空配管」という選択肢
ここで特に推奨したいのが、「空配管(からはいかん)」の設置です。空配管とは、将来ケーブルを通すことを見越して、壁の中にあらかじめ配管(CD管など)だけを通しておく工事を指します。
たとえ新築時にカメラを設置しない場合でも、この空配管さえあれば、将来カメラが必要になった際に、壁を傷つけることなく簡単にケーブルを通線できます。
防犯カメラの技術は日進月歩であり、数年後にはより高性能なカメラが主流になっている可能性が高いです。
空配管があれば、将来的なカメラの交換や増設、システムのアップグレードにも柔軟に対応できるため、長期的な視点で見ても非常に賢明な投資と言えます。
注文住宅の防犯カメラ用コンセントの計画

注文住宅のソコが知りたい・イメージ
防犯カメラシステムを安定して稼働させるためには、適切な電源確保が不可欠です。
そのためのコンセント計画は新築の設計段階で済ませておくべき重要な項目です。
考慮すべきコンセントは、主に「録画機(レコーダー)用」と「屋外カメラ用」の二種類に分けられます。
まず、録画機用のコンセントです。録画機は24時間365日稼働するため、安定した電源供給が求められます。設置場所としては、普段あまり人の目に触れず、機器の管理がしやすい場所がいいですね。
これらの場所に、あらかじめ録画機とモニター用のコンセントを計画的に設けておくことで、配線がごちゃつくことなく、すっきりとシステムを収めることが可能です。
次に、屋外に設置するカメラ本体の電源です。PoE(Power over Ethernet)給電に対応したシステムであれば、LANケーブル一本で映像と電源を供給できるため屋外にコンセントは不要です。
ただし、落雷に弱いなどのデメリットがあるため、注意が必要です。
しかし、ACアダプターで電源を取るタイプのカメラを設置する場合は、カメラの近くに屋外用の防水コンセントが必要になります。
後から屋外コンセントを増設するのは手間も費用もかかるため、カメラの設置場所を決める際に、コンセントの位置も併せてハウスメーカーや工務店に伝えておくことが肝心です。
ワイヤレスカメラを選ぶ際の注意点
ワイヤレス(Wi-Fi)防犯カメラは、配線の手間が少ないことから、特に後付けの場合に人気があります。
しかし、その手軽さの裏にある注意点を理解せずに導入すると、「いざという時に映っていなかった」という事態になりかねません。
特に、コンクリートや鉄骨の壁は電波を遮断しやすく、屋外に設置したカメラの映像が室内にあるルーターまで届かず、頻繁に途切れたり、全く見られなくなったりするケースは少なくありません。
設置を検討する際は、必ずスマートフォンのWi-Fi電波強度などを参考に、安定した通信が可能かを確認する必要があります。
次に、電源の問題です。ワイヤレスと言っても、多くは映像の送受信を無線で行うだけで、カメラ本体への電源供給はACアダプターなどで行う必要があります。
完全ワイヤレスを謳うバッテリー式のカメラもありますが、定期的なバッテリーの充電や交換が必須です。充電を忘れている間に事件が起きては元も子もありません。
さらに、セキュリティリスクも考慮すべきです。
防犯のためのアイテムがセキュリティリスクを高めるなんて笑えない話です。
ワイヤレスカメラを選ぶ際は、これらのデメリットを十分に理解した上で、安定性とセキュリティを確保できる環境を整えることが大切です。
戸建てに防犯カメラを自分で設置できる?

注文住宅のソコが知りたい・イメージ
防犯カメラの設置を考えた際、コストを抑えるために「自分で設置(DIY)できないか」と考える方もいるでしょう。
結論から言うと、設置するカメラの種類や場所によっては、自分で取り付けることも可能です。
壁への固定も、下地センサーで柱の位置を確認し、適切なネジを使えば、DIYに慣れた方であれば対応できるかもしれません。
しかし、有線カメラの設置や、屋外の高所への取り付けとなると、話は別です。
壁の中に配線を通したり、屋外用の防水処理を施したりするには、電気工事の専門知識と技術が求められます。特に、電源に関わる配線工事は、電気工事士の資格がなければ行うことができません。
不適切な工事は、漏電や火災の原因となるだけでなく、建物の防水性や断熱性を損なうリスクも伴います。
そこで、専門業者に依頼するメリットが大きくなります。業者は、防犯のプロとしての知見から、死角が少なく最も効果的な設置場所やカメラの種類を提案してくれます。
高所作業も安全に行い、建物の構造を理解した上で確実な取り付けと配線工事を実施してくれるでしょう。
もちろん工事費用はかかりますが、長期的な安心感と確実な防犯効果、そして何より安全性を考慮すると、特に新築の注文住宅においては、専門業者への依頼が最も賢明な選択と言えます。
気になる防犯カメラの新築設置費用
注文住宅に防犯カメラを設置する際の費用は、導入方法(購入かレンタルか)やカメラの台数、性能、そして工事の内容によって大きく変動します。
購入する場合の費用
カメラを購入して設置する場合、まず「初期費用」がかかります。これには、防犯カメラ本体、映像を記録するレコーダー、映像を確認するモニターの費用が含まれます。
カメラ本体は1台あたり1万円程度の安価なものから、高機能なモデルでは5万円以上するものまで様々です。
これに加えて、専門業者に設置を依頼する場合、1台あたり1万円~3万円程度の工事費が別途必要となります。
例えば、4台のカメラを設置する場合、機器代と工事費を合わせて10万円~20万円程度が一つの目安となるでしょう。
初期費用に加えて、「ランニングコスト」も考慮しなければなりません。
主に電気代と、録画データをクラウドに保存する場合の月額利用料(500円~1,500円程度)です。
また、レコーダーのハードディスクは約3年程度で寿命を迎えることが多く、交換費用などのメンテナンスコストも将来的に発生します。
レンタルする場合の費用
一方、レンタルサービスを利用する方法もあります。レンタルの最大のメリットは、初期費用を大幅に抑えられる点です。
月額料金制で、カメラ2台で月々4,800円程度から利用できるプランなどがあります。
この月額料金には、機器のレンタル代だけでなく、設置工事費やメンテナンス、故障時の交換費用が含まれていることが多く、手軽に始めたい方や、機器の管理に手間をかけたくない方には適しています。
ただし、長期間利用し続けると、総支払額は購入するよりも高くなる傾向があります。
ご自身の予算や利用期間、メンテナンスに対する考え方を基に、購入とレンタルのどちらが適しているかを検討することが大切です。
総括:後悔しない注文住宅の防犯カメラ選び
最後に、記事のポイントをまとめます。
- 注文住宅の防犯対策として防犯カメラは有効な選択肢の一つ
- 自身でカメラを設置している割合はまだ低いが重要性は増している
- 警察の犯罪捜査では映像データが検挙に大きく貢献している
- 「治安が良い」「費用がかかる」などの理由で不要と考える意見もある
- 設置の最大のメリットは侵入窃盗などに対する高い犯罪抑止効果
- 万が一の際には録画映像が有力な証拠となる
- デメリットは初期費用や維持費、プライバシーへの配慮が必要な点
- 後悔しないためには新築計画の初期段階で設置を検討することが鍵
- 新築時に設置すれば配線を壁内に隠蔽でき住宅の美観を損なわない
- 将来の交換や増設を見越した「空配管」の設置が非常に有効
- 録画機や屋外カメラのためのコンセント計画も設計段階で済ませるべき
- ワイヤレスカメラは手軽だが通信の不安定さや電源の問題に注意
- 有線カメラの設置や高所作業は安全と確実性のため専門業者への依頼が推奨される
- 費用は購入とレンタルで異なり予算や考え方に合わせて選択する
- 目的や予算、欲しい機能を明確にしてからプロに相談することが失敗しないコツ

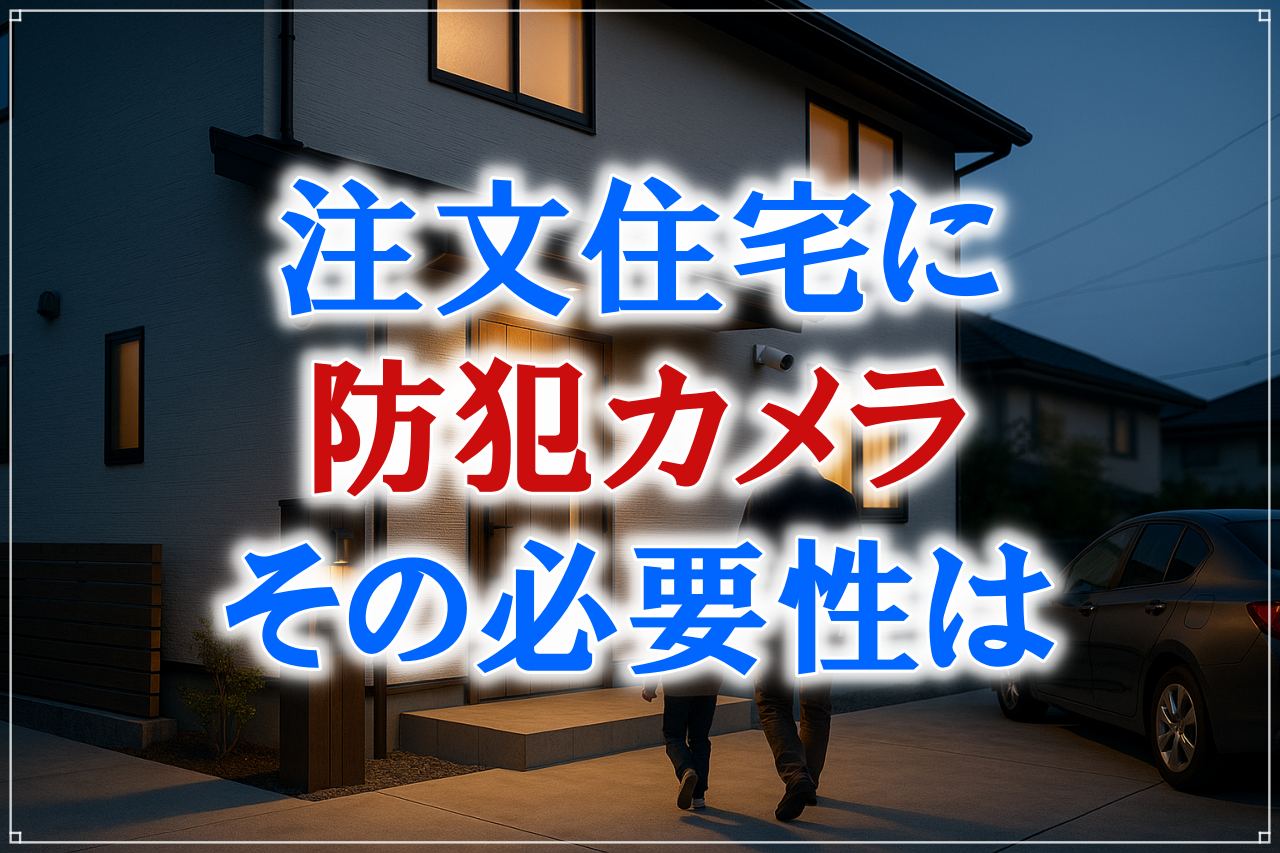
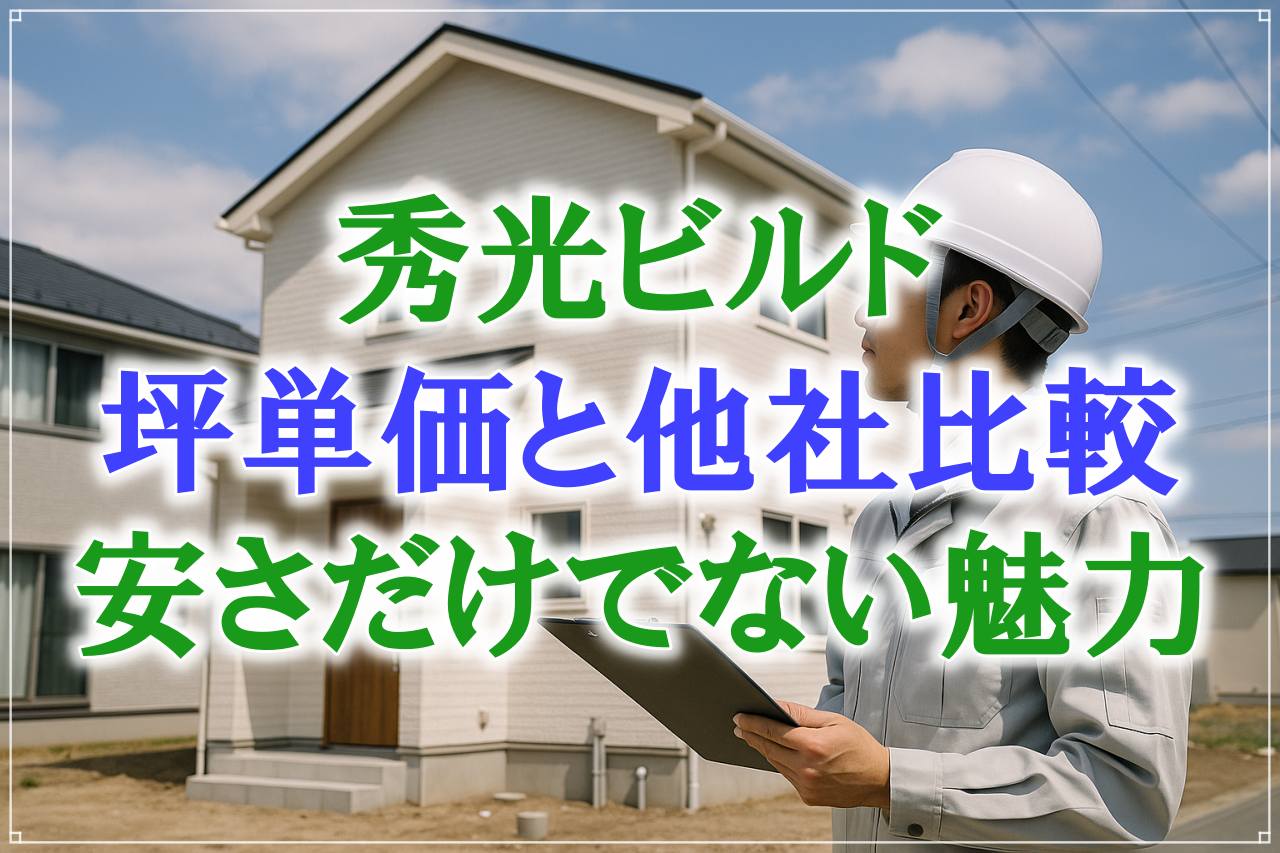
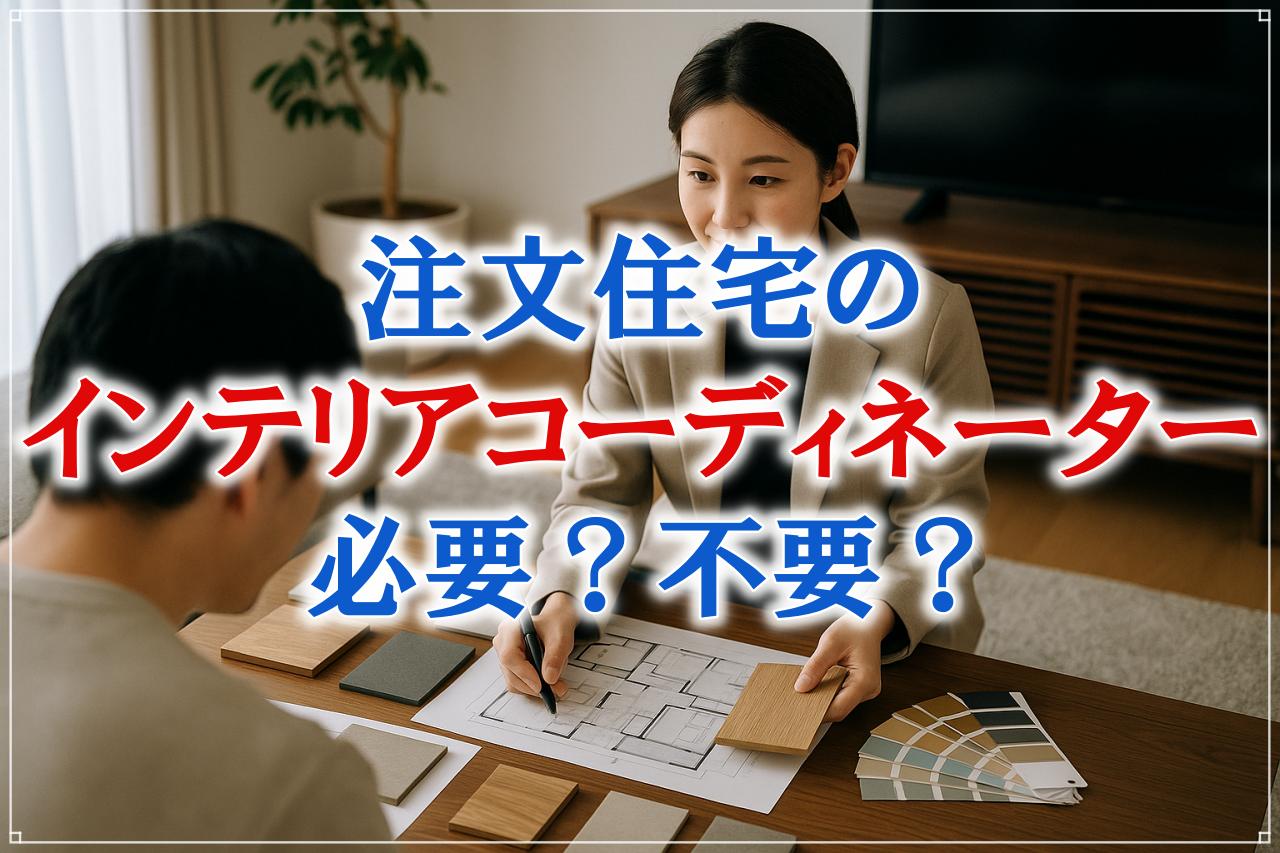
コメント